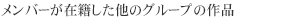Shades Of Deep Purple
1.And The Address
2.Hush
3.One More Rainy Day
4.(a)Prelude: Happiness (b)I'm So Glad
5.Mandrake Root
6.Help
7.Love Help Me
8.Hey Joe
Rod Evans writes and sings.
Jon Lord writes, sings and plays the organ.
Nic Simper writes, sings and plays the bass guitar.
Ritchie Blackmore writes and plays the lead guitar.
Ian Paice writes and plays the drums.
Producer : Derek Lawrence
1968 Warner Bros. Records Inc.
2.Hush
3.One More Rainy Day
4.(a)Prelude: Happiness (b)I'm So Glad
5.Mandrake Root
6.Help
7.Love Help Me
8.Hey Joe
Rod Evans writes and sings.
Jon Lord writes, sings and plays the organ.
Nic Simper writes, sings and plays the bass guitar.
Ritchie Blackmore writes and plays the lead guitar.
Ian Paice writes and plays the drums.
Producer : Derek Lawrence
1968 Warner Bros. Records Inc.

ディープ・パープルの、これがデビュー作である。タイトルを「Shades Of Deep Purple」という。ヒット曲の「Hush」が収録されていたことから、日本では「ハッシュ」というタイトルが付けられたものだった。リッチー・ブラックモアとジョン・ロード、イアン・ペイスという「ディープ・パープルの顔」とでも言うべきメンバーに加えて、ヴォーカルのロッド・エヴァンス、ベースのニック・シンパーの五人によってバンドは構成されていた。「ハード・ロック」のバンドとして一躍名を馳せる前の、いわゆる「第一期」ディープ・パープルである。
ディープ・パープルもまた、メンバーの交替とともにその音楽性を大きく、あるいは微妙に変化させてきたバンドだった。今から思えば、その経歴のすべての場面で、彼らの音楽は「ハード・ロック」の潮流の中に位置するものと考えることもできると思うのだが、この「第一期」ディープ・パープルが「ハード・ロック」の文脈の中で語られることは少ない。多くのロック・ファンにとって、「第一期」のディープ・パープルと「In Rock」以降のディープ・パープルの音楽性の差異はあまりにも大きく、両者の音楽は異質なものとして感じられるのかもしれない。

デビュー間もないディープ・パープルは、まずアメリカで人気を得た。意外なことかもしれないがイギリスではほとんど無名だったのだという。デビュー・シングルとなった「Hush」はアメリカのシンガー、ジョー・サウスの楽曲をカヴァーしたもので、1968年9月には全米ビルボード・チャートの4位を獲得している。ちなみにその年の夏のビルボード・チャートにはローリング・ストーンズの「ジャンピン・ジャック・フラッシュ」、クリームの「サンシャイン・ラヴ」、ヴァニラ・ファッジの「ユー・キープ・ミー・ハンギン・オン」、ドアーズの「ハロー・アイ・ラヴ・ユー」、ラスカルズの「自由への賛歌」、ステッペンウルフの「ワイルドで行こう」といった楽曲が、さまざまなポップ・ソングに混じってトップ10に登場する。9月14日のチャートではビートルズの「ヘイ・ジュード」が10位に初登場し、28日にはトップに登り詰め、9週間連続のトップという成果を残している。そんな時代だった。
このディープ・パープルのデビュー作には、確かにそのような時代の空気がある。ロック・ミュージックがさまざまなサブカルチャーを取り込みながら拡大し、新たな方法論を身に付けていこうとしていた時代の空気だ。デビューしたディープ・パープルの音楽もまたそうした時代に呼応し、ロック・ミュージックの進化の過程の中から必然的に生み出されてきたスタイルのものであるようにも思える。ヴァニラ・ファッジやアイアン・バタフライといったバンドとの共通性をそこに垣間見ることもできる。当時「アート・ロック」の呼称を与えられたスタイルのひとつだったと言えるかもしれない。

「第一期」ディープ・パープルの音楽的主導権は、おそらくジョン・ロードとロッド・エヴァンスにあったのだろう。その音楽の中心となっているのはジョン・ロードの奏でるオルガンとロッド・エヴァンスの歌声だ。「In Rock」以降は「リッチー・ブラックモアこそがディープ・パープル」という認識が一般的になってゆくが、「第一期」の彼らは「ロッドの歌唱とジョンのオルガンこそがディープ・パープル」であった。
ロッド・エヴァンスの歌唱は決して「シャウト」することはない。ディープ・パープルの音楽を印象づける上での、「第二期」以降との最も大きな違いのひとつがそこにある。そもそも当時のロック・ミュージックに於けるヴォーカル・スタイルでは「シャウト」は一般的なものではなかった。「シャウト」するスタイルのヴォーカルは「ハード・ロック」の基本的な骨格ができあがる過程で、ロック・ミュージックが必然的に獲得したものだと言えるだろう。ギタリストの演奏とヴォーカリストの歌唱とが、時に戦いを挑むように、時に競い合うように、その存在感を示し、それぞれに緊張感を伴った歌唱と演奏とが互いに拮抗することによってさらに緊張感を生むという「ハード・ロック」の方法論は、ジェフ・ベック・グループとレッド・ツェッペリンの登場を待たなくてはならかった。ロッド・エヴァンスの歌唱は、ロック・ミュージックがそうした方法論を獲得する以前のスタイルだ。
しかし、だからと言ってロッド・エヴァンスの歌唱が魅力的ではないということではないし、「非力」であるということでもない。ロッドの歌声はロマンティックで陰影に富み、味わいのあるものだ。旋律の美しい楽曲と、重厚な演奏のロック・ミュージックに、その歌唱はよく似合っており、流麗な印象も伴ってディープ・パープルの独特の音世界を現出することに成功している。
ロッド・エヴァンスの歌声を中心に据えながら、しかしその演奏自体は非常にエキサイティングでアグレシッシヴ、スリリングな魅力のあるロック・ミュージックだ。リッチー・ブラックモアのギターは「第二期」以降でのプレイと比べても遜色なく、かえってその若さに任せたプレイが小気味よく痛快だ。そうした演奏を繰り広げながらもこの時期のディープ・パープルの音楽が「ハード・ロック」として成立し得ないのは、ただ単に当時の彼らの指向が後の「ハード・ロック」とは異なるスタイルであったということに過ぎないのだろう。

冒頭の「And The Address」はヴォーカル無しのインストゥルメンタル曲だ。リッチー・ブラックモアとジョン・ロードによる楽曲で、演奏そのものも両者が拮抗しつつ繰り広げてゆく様がエキサイティングだ。「Hush」はシングルとなってヒットしたこともあって、当時のディープ・パープルをよく知らない人にも耳に馴染みのある楽曲であるかもしれない。狼らしき獣の遠吠えから始まる導入部も印象的だ。楽曲自体はポップなものだが、ディープ・パープルの演奏によって魅力的なロック・ミュージックに変貌していると言ってよいだろう。
「One More Rainy Day」はジョン・ロードとロッド・エヴァンスによる楽曲で、ロマンティックなメロディが魅力だ。雷鳴の音に被さるように始まるジョン・ロードのオルガンの演奏も印象的だ。このような楽曲にはロッドの歌声はとてもよく似合っており、「第一期」ディープ・パープルのクラシカルで翳りのある印象をよく表しているものと言えるだろう。「Happiness」から「I'm So Glad」へと続く四曲目は電子音によって始まる導入部と、少しばかり荘厳さを感じさせるジョン・ロードのオルガンが「プログレッシヴ・ロック」的な魅力を感じさせてくれる。この楽曲もまた「第一期」ディープ・パープルの魅力を象徴するものだ。
「Mandrake Root」は、「ハード・ロック」である。イアン・ギランを擁した「第二期」のメンバーによる「Scandinabian Nights」の20分超という演奏を知るものにとっては、その原型をここに見ることができるとも言える。間奏部で聞かれるエキサイティングな演奏は、「第二期」で完成する「ハード・ロック」としてのディープ・パープルの音楽そのものだと言えるだろう。「Help」はビートルズの楽曲のカヴァーだが、まったく異なった解釈のもとに少しばかり夢想的な味わいを感じさせる演奏として提示されている。ロッド・エヴァンスのロマンティックな歌唱の魅力を味わえる一曲と言えるかもしれない。
「Love Help Me」も奇妙な効果音による導入部が印象的だ。ポップな曲調の楽曲だがエキセントリックなブラックモアのギターがアクセントになっている。ブラックモアとエヴァンスの共作になる楽曲である。最後の「Hey Joe」も効果音から始まり、ジョン・ロードのオルガンへと引き継がれ、やがてロッドの歌唱へと至る構成で、ボレロを基調にした演奏がクラシカルでドラマティックな印象の楽曲だ。演奏が終わった後、静寂の中に足音が聞こえ、ドアを閉じる音で作品は終わる。なかなか凝った作りがなされているのだ。

「第一期」ディープ・パープルの音楽は、その少々夢想的な印象のためか「プログレッシヴ・ロック」的な解釈がなされることもある。しかし、その演奏の中に見られるのは決して「プログレッシヴ・ロック」のイディオムではない。当時のディープ・パープルのオリジナル・メンバー達がどのような音楽を目指していたのかは知らないが、ここに見られる音楽はクラシカルで美しい旋律とエキサイティングでスリリングな演奏との融合、荘厳さも感じさせる音像の中のアグレッシヴな演奏のダイナミズム、そういったものであるように思える。この音楽で見られるジョン・ロードとリッチー・ブラックモアの演奏は、このまま「第二期」以降の彼らの音楽に持ち越されるものと同等のものだ。「第一期」ディープ・パープルの音楽が「ハード・ロック」でないのは、当時のロック・ミュージック・シーンが未だ「ハード・ロック」を知らなかったことによるのかもしれない。
ロッド・エヴァンスのヴォーカルは甘く柔らかな印象があり、それがこの作品の全体の印象を決定しているとも言えるだろう。ジョン・ロードのオルガン演奏のクラシカルな印象もまた作品世界の印象を決定するもののひとつだ。リッチー・ブラックモアの演奏はスリリングでエキセントリックだが、この作品世界の中では中心とはなり得ず、「脇役」に甘んじている印象もある。それは決して「間違い」ではない。そうした印象はすなわち、当時の彼らのサウンド・コンセプトであったのに違いなく、ハードでアグレッシヴな演奏の魅力と陰影に富んだ音像、そして美しい旋律の魅力が一体となって彼らの作品世界を形作る結果をもたらしている。
1970年代以前のディープ・パープルがロック史の中に語られるようになった現在、「第二期」以降の成功のみが大きく語られ、「第一期」の彼らは時に軽んじられ、時に無視されるような場面も少なくはないように思える。しかし、「第二期」以降の彼らの音楽に比して「第一期」の音楽が劣っているというわけでは決してない。そもそも「第二期」以降の彼らの音楽と「第一期」の音楽とを比べてしまうことこそ無意味なことであるだろう。この作品に在るのは、若いミュージシャン達が瑞々しい感性のもとに造り上げた新しいロック・ミュージックのスタイルだ。後々の経緯を知る立場から見ればそれは後に独自の「ハード・ロック」へと発展してゆく要素を内包するものではあったが、そうしたことを視野の外に置いても、この音楽は充分に奥深く新鮮で魅力的だ。その音楽世界は彼らのバンド名「ディープ・パープル」にまさに相応しい印象を持っている。これが彼らの原点だ。
This text is written in May, 2002
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.