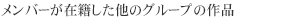サディスティック・ミカ・バンド / 加藤和彦とサディスティック・ミカ・バンド
1.ダンス・ハ・スンダ / Dance Is Over
2.怪傑シルヴァー・チャイルド / Siver Child
3.宇宙時計 / Cosmic Watch
4.シトロン・ガール(金牛座流星群に歌いつがれた恋歌) / Citron Girl
5.影絵小屋 / Shadow Show
6.空の果てに腰かけて / (I'm Sitting On) The Edge Of Sky
7.銀河列車 / Gallaxy Way
8.アリエヌ共和国 / Arienu Republic
9.恋のミルキー・ウェイ / Milky Way
10.ピクニック・ブギ / Picnic Boogie
11.サイクリング・ブギ / Cycling Boogie
Kazuhiko Katoh : vocal, guitars, synthesizer
Mika : vocals
Masayoshi Takanaka : guitars, synthesizer, melotron, voice
Rei Ohara : bass, marimba, vocal
Yukihiro Takahashi : drums, percussion, voice
Hiro Tsunoda:percussion
Hiroshi Imai:keyboards
Hiroshi Shigemi : piano
Kazumasa Oda : piano
Steaven Israel : synthesizer
Produced by Kazuhiko Katoh
1973
2.怪傑シルヴァー・チャイルド / Siver Child
3.宇宙時計 / Cosmic Watch
4.シトロン・ガール(金牛座流星群に歌いつがれた恋歌) / Citron Girl
5.影絵小屋 / Shadow Show
6.空の果てに腰かけて / (I'm Sitting On) The Edge Of Sky
7.銀河列車 / Gallaxy Way
8.アリエヌ共和国 / Arienu Republic
9.恋のミルキー・ウェイ / Milky Way
10.ピクニック・ブギ / Picnic Boogie
11.サイクリング・ブギ / Cycling Boogie
Kazuhiko Katoh : vocal, guitars, synthesizer
Mika : vocals
Masayoshi Takanaka : guitars, synthesizer, melotron, voice
Rei Ohara : bass, marimba, vocal
Yukihiro Takahashi : drums, percussion, voice
Hiro Tsunoda:percussion
Hiroshi Imai:keyboards
Hiroshi Shigemi : piano
Kazumasa Oda : piano
Steaven Israel : synthesizer
Produced by Kazuhiko Katoh
1973

「帰ってきたヨッパライ」や「悲しくてやりきれない」といったヒット曲で一世を風靡した「ザ・フォーク・クルセダーズ」が解散した後、加藤和彦は北山修と組んで「あの素晴しい愛をもう一度」を発表、1971年の大ヒット曲になった。同じ年、加藤和彦はつのだひろの協力を得てソロ・アルバム「スーパー・ガス」を制作発表している。つのだひろはすでに当時からよく知られたドラマーだった。この頃から加藤和彦はロックを志向していたのだろう。加藤とつのだのふたりは、当時の加藤和彦夫人だったミカとともに「サイクリング・ブギ」を制作する。「サイクリング・ブギ」は加藤が設立したプライベート・レーベル「ドーナツ・レコード」から1972年にシングルとして発売される。名義は「サディスティック・ミカ・バンド」だった。「サディスティック・ミカ・バンド」はそのままバンド形態へと発展する。ギターは高中正義だった。高中はつのだひろと成毛滋とのトリオ「フライド・エッグ」のベーシストだったが、本来は才能溢れる若いギタリストだった。ベースの小原礼はこの頃、高橋幸宏とともに「ガロ」のバックで演奏していた。ガロは1971年にデビュー、1972年には「学生街の喫茶店」が大ヒットになっていた。バンドの結成に携わったつのだは、しかし自身のバンド結成のためにすぐに脱退、その後任のドラマーとなったのが高橋幸宏だった。このメンバーによって「サディスティック・ミカ・バンド」は1972年の暮れにステージ・デビュー、アルバムの制作に取りかかった。完成したアルバムは1973年5月、「サディスティック・ミカ・バンド」のタイトルで発表される。名義は敢えて「加藤和彦とサディスティック・ミカ・バンド」とされた。アルバムは全10曲を収録し、「サイクリング・ブギ」がボーナス・シングルとして付加されるという異色の構成だった。

サディスティック・ミカ・バンドが誕生し、デビュー・アルバムを発表した1972年から1973年にかけて、日本のポップ・ミュージック・シーンではフォークが台頭し、アイドル歌謡が隆盛の時期を迎えようとしていた。1972年にはよしだたくろうの「旅の宿」や青い三角定規の「太陽がくれた季節」、1973年にはかぐや姫の「神田川」やチェリッシュの「てんとう虫のサンバ」、あるいは浅田美代子の「赤い風船」や天地真理の「恋する夏の日」といった曲が大ヒットになった。同じ頃、遠く離れたイギリスでは「ハード・ロック」と「プログレッシヴ・ロック」が隆盛の時期を迎え、ロンドンでは「グラム」が艶やかに咲き誇っていた。日本のロック・シーンもようやく試行錯誤を繰り返した黎明期の混迷を抜け出し、発展の時代を迎える気配はあったが、海外のロック・ミュージック、特に英国のロックを聴き親しんでいたロック・ファンにとって、とても満足できる状況ではなかった。レッド・ツェッペリンやブラック・サバス、キング・クリムゾン、イエスといったバンドたちの圧倒的な魅力を放つロック・ミュージックを愛するファンにしてみれば、当時の日本のロック・バンドのほとんどは音楽的なスケール感に乏しく、心を沸かせるカリスマ的な「ロックの匂い」が足りなかった。
そのような状況だったから、サディスティック・ミカ・バンドのデビューは衝撃的だった。それまでの日本のロックのベクトルは、「欧米のロックに追いつけ」という側面が強かったことは否定できない。特にブリティッシュ系のロックを志向するバンドたちにとっては、英国のブルース・ロック、ブルース系ハード・ロックへの信奉にも似た想いがあっただろう。「ロックというものはああでなくてはならない」といった闇雲な信念があったのではないか。彼らは英国のロック・ミュージシャンに倣って髪を伸ばし、ベルボトムのジーンズを履き、求道的といってもいいような姿勢で音楽に立ち向かった。そこへ、ファッショナブルな衣装に身を包み、派手で艶やかなサウンドを煌めかせてサディスティック・ミカ・バンドが登場した。彼らの音楽には求道的なブルース・ロックへの志向は感じられなかった。その音楽にあったのは当時ロンドンを席巻していた「グラム・ロック」の匂いだった。
信じられないかもしれないが、当時、「グラム・ロック」は時代の徒花のように扱われる傾向があった。ボラン・ブギーやジギー・スターダストがミュージック・シーンを賑わせていても、それらは一過性の浅薄な流行音楽に過ぎないと思われていた。そうでなかったことはすでに時代が証明しているが、当時、「グラム・ロック」は「ロック」の本流から外れた、いやもっと言うなら「ロック」とも呼べないようなヒット・ポップスに過ぎないとする見方が多かった。派手な衣装や奇をてらった演出で一時期の人気を得ていても、やがて時代が移れば人気を失い、忘れ去られてしまうような、その程度のものだと思われていたのだ。だから、その「グラム」の匂いをふりまきながら登場したサディスティック・ミカ・バンドは、当時の日本ロック・シーンのベクトルを超えて異彩を放つ存在だったと言っていい。
サディスティック・ミカ・バンドの音楽は、カラフルでグラマラスでファッショナブルでダンサブルなロックだった。彼らの音楽は基本的にポップでわかりやすく、陽気で楽しく、「ノリ」がよく、肩肘を張らず、気負いがなく、そしてまた加藤和彦自身の言葉を借りれば「汗くさくない」ロックだった。その音楽は色彩感覚に溢れ、ぎらぎらと艶めかしく煌めき、享楽的な匂いを放ちながらも、知的で真摯な品格を失っていなかった。それはまるで当時の日本ロックへのひとつのアンチテーゼだったかもしれない。本場欧米のロックに追いつこうとしながら、しかし追いつくことのできないもどかしさに足掻きながら、まるで「ロックの教義」に縛られたような当時の日本ロック・シーンを嘲笑うような痛快さが、サディスティック・ミカ・バンドのロックには、あった。「おまえたち、考えすぎじゃないのか」と、彼らのロックは言っているようだった。
そもそもサディスティック・ミカ・バンドのリーダーである加藤和彦はザ・フォーク・クルセダーズや「あの素晴しい愛をもう一度」で一世を風靡したミュージシャンであり、いわば「フォーク畑」の出身だった。1960年代末の「グループ・サウンズ」期から1970年前後の「ニュー・ロック」期へと活動を継続してきた「ロック畑」のミュージシャンたちとは「ロック」に対するベクトルが違っていても不思議ではない。サディスティック・ミカ・バンドは、当時の他の日本ロックのバンドたちとは「ロック」への向き合い方がまるで違っているように見えた。
その加藤和彦率いるサディスティック・ミカ・バンドが当時の日本ロック・シーンで第一級のロック・バンドになり得たのは、そのメンバーたちの演奏の並外れた力量によるものだったろう。今から考えれば当然のことだが、ギターの高中正義、ベースの小原礼、ドラムの高橋幸宏の三人も、当時の音楽シーンで最も注目すべきミュージシャンとして知られた人たちだった。その演奏の技術、センスともに申し分のないものだった。そして、ミカだ。彼女は決して上手いシンガーではなかった。いや、有り体に言えば歌は下手だった。しかし彼女の存在は強烈に「ロック」のオーラを放った。上手くない歌声の響きさえ、「ロック」の匂いに満ちていた。彼女こそが「サディスティック・ミカ・バンド」と、彼らの「ロック」の象徴だった。そしてサディスティック・ミカ・バンドは日本ロック黎明期の混沌から一気に浮上してゆく。

このデビュー・アルバムに収録された楽曲はいずれも基本的にわかりやすいメロディ・ラインを持ったポップ・ソングだが、それがバンドのメンバーたちのセンスの良い演奏によって派手で煌びやかな印象の「ロック」の意匠を身に付けているという印象がある。ハードなロックン・ロールやブギ、ルーズな感じのロックン・ロール、レゲエ風の味付けのものまで、さまざまな曲調の楽曲が並んで飽きさせない。レゲエ風のリズムを持った演奏は、当時の日本ロック・シーンに於いて他に類例がないのではないか。シンセサイザーまで駆使した演奏は「プログレッシヴ・ロック」のイディオムさえ含んだものだが、実験的な先進性からは潔く背を向け、あくまでダンサブルなロックン・ロールの楽しさという点に重きが置かれた演奏だ。
アルバムに収録された楽曲のほとんどは、松山猛が詞を書き、加藤和彦が曲を書いている。例外はミカ作詞、高中正義作曲の「怪傑シルヴァー・チャイルド」、高橋幸宏作曲による「恋のミルキー・ウェイ」と「ピクニック・ブギ」、そしてつのだひろ作詞の「サイクリング・ブギ」に過ぎない。だからこのアルバムは加藤和彦の類い希なメロディー・メーカーとしての才能が存分に発揮されたアルバムだと言ってもいい。そしてもちろん、高中正義、高橋幸宏、小原礼というミュージシャンたちの演奏もアルバムの魅力だ。高橋幸宏と小原礼は当時、R&Bやファンクといった音楽を志向していたらしいが、フォークをルーツに持つ加藤和彦の音楽性とうまく融合してこのような素晴らしいロックが誕生したのだろう。彼らの後の活躍を知っている現在になってこのアルバムを聞くと、彼らの演奏がなぜこれほどまでに魅力的なのかということにも納得がいく。
どの楽曲もそれぞれに魅力があって甲乙付けがたいが、ハードに突っ走る「ダンス・ハ・スンダ」や甘美なメロディの中に哀感を滲ませた「シトロン・ガール」などが印象深い。特に「シトロン・ガール」は名曲と言っていいのではないか。そして何より、このアルバムの白眉は「ピクニック・ブギ」だ。ミカがリード・ヴォーカルをとったこの楽曲こそは、初期のギラギラとした魅力を放ったサディスティック・ミカ・バンドを象徴する楽曲だと信じて疑わない。サディスティック・ミカ・バンドの代表曲と言えば、次作「黒船」に収録され、シングルとしてもヒットした「タイムマシンにお願い」で異論のないところだが、初期サディスティック・ミカ・バンドの魅力を最も象徴的に具現化した楽曲をひとつ挙げるとすれば、個人的には圧倒的に「ピクニック・ブギ」だ。T.Rexの演奏、いわゆる「ボラン・ブギー」を濃厚に感じさせる演奏も素晴らしいものだが、何しろミカのヴォーカルが凄い。ミカのヴォーカルは、下手だ。まるっきり素人だと言っていい。それなのに、その歌声が放つ圧倒的なまでのロックとしての迫力は何なのか。その強烈な印象こそが、サディスティック・ミカ・バンドを「ロック・バンド」として成立させているのだと言っても過言ではない。歌唱技術の未熟さ故にミカのヴォーカルに否定的な意見も少なくはないが、しかしミカの歌唱は技術云々を超えてロックのオーラを放っている。ミカの歌唱とその存在そのものに、ロックというものの本質を見たファンは少なくないのではないか。ミカのヴォーカルが後のニュー・ウェイヴ系の女性ヴォーカリストに少なからぬ影響を与えたという意見もある。おそらく間違っていないだろう。

当時の日本ロック・シーンではかなり画期的な方法論を携えてデビューしたサディスティック・ミカ・バンドだったが、デビュー直後の彼らは決して順風満帆というわけではなかった。メディアでもそれほど評判にならなかったし、商業的にもデビュー・アルバムは当初あまり売れなかった。彼らのデビューとほぼ同時期、リーゼントに革ジャンというスタイルに身を包み、1950年代風のロックン・ロールを演奏するキャロルがデビューし、一気に人気を得てセンセーショナルな話題をさらった。瞬く間にキャロルは日本の「ロック」を代表するバンドとして認知され、サディスティック・ミカ・バンドはその余波を受けて片隅に追いやられた観もあった。キャロルもまた当時の日本ロック・シーンに痛烈なアンチテーゼを呈したバンドだったが、当時の日本ロックが目指した方向とはあまりに異なったベクトルを持っていたのは確かだった。
デビュー・アルバムを完成させたサディスティック・ミカ・バンドのメンバーは、休養を兼ねてロンドンを訪れたという。そもそも加藤和彦をはじめ、バンドのメンバーたちはロンドンが好きだったようだ。どのような経緯だったかという点については加藤和彦や他のメンバーたちのインタビューなどに譲るが、サディスティック・ミカ・バンドのデビュー・アルバムはロンドンの一部の関係者に渡り、徐々に話題を集めてゆく。そうしてクリス・トーマスからのオファーを受ける形で次作のクリス・トーマスによるプロデュースが実現する。このニュースは当時の日本ロック・シーンで大きな話題になった。次作「黒船」のレコーディングも終わった1974年5月、サディスティック・ミカ・バンドのデビュー・アルバムが英国で発売された。日本人のバンドによって日本で作られ、日本語で歌われたロック・アルバムが英国で発売されたのだ。それは当時の日本ロックの、ひとつの「誇り」だった。
This text is written in April, 2007
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.