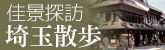埼玉県飯能市は古くから栄えた町だ。江戸時代中頃には町が形成され、材木の産地として大いに発展した。明治期になると絹織物や木綿縞の産地としても栄えた。当時の飯能は入間郡の中でも有数の規模を誇り、川越や所沢に並ぶほどだったという。大正の時代になって武蔵野鉄道(現在の西武池袋線)が敷設された後は林業がさらに発展し、観光業でも人気を集めた。戦後になって林業や繊維業は衰退したが、かつての繁栄を背景に独特の存在感を漂わせる町だと言っていい。飯能市の中心市街、特に西武池袋線飯能駅の北西側に位置する仲町周辺は往時の繁栄の面影を残しており、細い路地や古い建物などを訪ねての散策が楽しい。
西武池袋線飯能駅の北口周辺が飯能市の中心と言っていいようだ。駅前にはロータリーが設けられ、西側には複合商業ビルが建つ。ロータリーから北へ県道228号が延び、これが飯能市のメインストリートといった風情だ。駅側には「HANNO」と書かれたモニュメント風のアーチが設けられ、駅を降り立った人たちを出迎えている。駅前ロータリーから西へ線路沿いに延びる道には「材木通り」という愛称があるようだが、これはかつて林業で栄えた当時の名残か。
飯能駅北口の駅前交差点から県道228号を北へ辿ると、80mほどのところで細い道が西へ延びる。「南裏通り」だ。さらに北へ進めば「飯能駅前」交差点だ。東から延びてきた国道299号がここで北へ折れて続く。だから県道228号は駅前から「飯能駅前」交差点までの、約130mの短い区間の県道なのだ。「飯能駅前」から西へ向かうのは飯能銀座通り、商店街となっていて、西から東への一方通行だ。
「飯能駅前」交差点から100mほど北へ進んだところで「東町」交差点だ。東へ延びるのは県道185号、西へ延びるのは県道28号だ。“西へ延びる”と書いたが、実は「東町」交差点は青梅市から延びてきた都県道28号の終点である。
この駅前から北へ延びる道路と、西は飯能河原の河岸近く、北は県道28号、南は材木通りに囲まれた辺りが、仲町(なかちょう)の町域だ。「東町」交差点から県道28号を西へ500mほど辿ったところに「仲町」交差点がある。おそらく「仲町」交差点の南側辺りが、仲町の中心地だったのだろう。
「飯能駅前」交差点から飯能銀座通りへと歩を進めると、交差点から80mほどのところにおもしろい案内板がある。「飯能まちなかを元気にする会」の名で、「飯能でいちばん狭く、短い?公道」と矢印が示されている。「通り抜けできます。」ともある。案内板が無ければ見過ごしてしまいそうな細い路地が建物と建物の間に延びている。路地歩き好きの心をくすぐる細さだ。路地は70mほどで南裏通りへ抜け出る。短さはともかく、狭さは確かに飯能でいちばんかもしれない。
“飯能でいちばん狭く短い?公道”の入口から銀座通りを西へ40mほど進むと、「旅籠横丁」という細道が南へ延びている。これも南裏通りまで80mほどの距離だ。「旅籠横丁」の名は通りの中ほどに旅館があるからか。旅館はなかなか風情漂う外観だ。今でも営業されているようである。
「旅籠横丁」の入口からさらに銀座通りを西へ40mほど、通りの南側に伊勢屋という店がある。団子や大福を販売しているのでいちおう和菓子店と言っていいのだろうと思うが、扱う商品はさらに惣菜や巻き寿司、ちらし寿司、いなり寿司、おにぎり、お弁当など多岐に及ぶ。なかなかの人気店のようで、ひっきりなしにお客さんが訪れる。ほとんど常連さんのようだ。
伊勢屋は店内での飲食も可能だ。あんみつやおしるこなどの甘味の他、簡単な食事メニューもある。伊勢屋で“ミニぜんざい付き”のうどんのセットメニューをいただいた。うどんは腰があり、出汁がよく利いて塩味も強すぎずおいしい。“ミニぜんざい付き”というのも嬉しい。ぜんざいはかなり濃い。そこに焼いた餅がひとつ載っている。うどんとぜんざい、素敵な組み合わせだ。
伊勢屋の西側から南へ延びるのが伊勢屋横丁だ。伊勢屋横丁も90mほどの距離で南裏通りまで延びている。横丁沿いには古い建物も残っており、良い風情を漂わせている。路地には「飯能まちなかを元気にする会」による横丁の名を記したプレートが設置されている。他の横丁にもこうしたプレートがあり、町を散策する身としては嬉しい。
伊勢屋の30mほど西、銀座通りの北側に洋風の意匠の建物が建っている。傍らに「入間馬車鉄道と看板建築」と題した解説板が飯能市教育委員会の名で設置されている。それによれば、この建物は五軒長屋の木造二階建てとして建てられたものという。その後、洋風の石積みを模した外壁を通りに面して元の建物を隠すように設けた。いわゆる「看板建築」だ。解説板には飯能の繁華街の歴史についても簡単な説明が記されている。ぜひ目を通しておきたい。
伊勢屋から銀座通りを西へ150mほど進むと県道218号との交差点だ。変則的な形状の交差点だ。県道218号は南の「稲荷分署入口」交差点から北上してきて、ここで少し西へ折れて緩やかに曲がりながら北へ延び、県道28号との「広小路」交差点に至っている。東へ延びる銀座通りとは別に、市街地の中を抜けて斜めに南東の方角へ延びる道もある。道路の構成が変則的で、興味をそそられる。おそらく昔からの道筋の名残なのだろう。
銀座通りから「広小路」交差点へと出て、県道28号を少し東へ戻ってみる。「広小路」交差点から東へ150mほどのところ、県道28号の南側に飯能織物協同組合事務所の建物が建っている。1922年(大正11年)に現在の飯能織物協同組合の事務所棟として建てられたもので、「飯能織物協同組合事務所棟 」として国の登録有形文化財(建築物)に登録されている。木造二階建ての洋風建築だが、寄棟造桟瓦葺の屋根には二基のシャチホコが据えられた、和洋折衷の意匠だ。
飯能織物協同組合事務所と「広小路」交差点との中間辺り、県道28号の南側に土肥歯科医院の建物が建っている。古い建物のようだが、薄いブルーに塗装された外観がなかなかおしゃれな印象だ。外壁には蔦が絡まっているが、廃屋というわけではなさそうだ。医院はひっそりとしている。土曜日のお昼過ぎ、すでに診療時間を終えられているのだろう。
「広小路」交差点から県道28号を西へ200mほど辿ると「仲町」交差点だ。丁字路の交差点で、ここから北へ高麗横丁が延びている。「広小路」交差点から「仲町」交差点に向かう途中、県道28号の路上に「飯能大通り商店街」と記されたアーチが設けられている。どうやら飯能市の市街地を通る県道28号には「飯能大通り」という愛称があるらしい。
「仲町」交差点から30mほど東側、県道28号の北側(本町側)に絹甚という店蔵が建っているが、その道路向(仲町側)にまんじゅう小路という名の細道が南へ延びている。「飯能まちなかを元気にする会」による案配板がある。それによれば、この小路の西側にかつて1848年(嘉永元年)創業のまんじゅう屋があったそうだ。案内板にはまんじゅう屋店主と戊辰戦争との関わりについても書かれている。これもぜひ目を通しておこう。
「仲町」交差点のすぐ西側、県道28号の南側(仲町側)に畑屋という店がある。畑屋は割烹料亭として創業、近年まで鰻の名店として知られていたようだが、現在は鰻店としては終業しており、春夏はかき氷、秋冬は鶏の肉まんの店として営業している。畑屋の創業は1902年(明治35年)、今も残る建物は大正期に建てられたものという。繁栄の名残を感じさせる、堂々とした建物だ。
畑屋の西側から南に延びる細道は畑屋横丁だ。畑屋横丁は畑屋の横から南裏通りや材木通りと交差しながら南へ300mほど延びている。畑屋横丁には婦美町小路(ふみちょうこうじ)という別名もあるようだ。横丁というには比較的広い道だが、なかなか良い風情の道だ。
畑屋の前から県道28号をさらに西へ進んで「飯能河原」交差点が近付いた辺り、交差点の40mほど手前に住宅の間を南に入り込む細道がある。この細道には特に名は無いようだ。県道28号から100mほど延びて南裏通りに至っている。かなりの細道で、しかも途中で屈曲しているから、県道側から見ても南裏通り側から見ても、通り抜けられるのかどうかわからず、歩を進めるのにためらってしまう。路地散歩好きにはお勧めの細道と言っていい。
南裏通りと畑屋横丁とが交差するところからのすぐ西側、南裏通り沿いに「四代目 高島屋」という日本料理の店が建っている。通り沿いの塀に簡単な解説を記した案内板が設置されている。それによれば、この辺りはかつて花街として賑わったところで、芸者衆の三味線や太鼓の音が響いていたそうだ。高島屋は当時は置屋で、その後に建て直され、料亭として引き継がれてきたという。飯能の繁栄の歴史を物語る店というわけだ。
飯能市仲町で散策を楽しむなら銀座通りと南裏通りを中心に、横丁に入り込んだりしながら気ままに歩き回ってみるのがお勧めだ。南裏通りもさまざまな横丁も、道そのものの風情が良く、町歩き好きの人なら充分に楽しいひとときを過ごすことができる。銀座通りも楽しい。もちろん大きな街の商店街に比べれば商店の数も人通りも少ないが、なかなか活気を感じる商店街だ。
かつての繁栄の名残を漂わせ、閑寂な中に日常が息づく飯能市仲町、レトロな風情を感じさせる町の好きな人にはお勧めのところだ。「飯能まちなかを元気にする会」の方々にはこの場を借りて謝意を表しておきたい。






























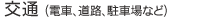




 飯能銀座商店街
飯能銀座商店街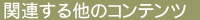
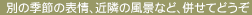

 飯能河原
飯能河原 晩秋の飯能河原
晩秋の飯能河原