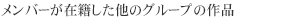Fields
1.A Friend Of Mine
2.While The Sun Still Shine
3.Not So Good
4.Three Minstrels
5.Slow Susan
6.Over And Over Again
7.Feeling Free
8.Fair-Haired Lady
9.A Place To Lay My Head
10.The Eagle
Graham Field : organ, electric piano and piano.
Alan Barry : vocals, lead and bass guitar, classical guitar and mellotron.
Andrew McCulloch : drums, timpani and talking drum.
Produced by “Fields”
1971
2.While The Sun Still Shine
3.Not So Good
4.Three Minstrels
5.Slow Susan
6.Over And Over Again
7.Feeling Free
8.Fair-Haired Lady
9.A Place To Lay My Head
10.The Eagle
Graham Field : organ, electric piano and piano.
Alan Barry : vocals, lead and bass guitar, classical guitar and mellotron.
Andrew McCulloch : drums, timpani and talking drum.
Produced by “Fields”
1971

フィールズ(Fields)というバンドのことを知っている人はかなり少ないのではないだろうか。「プログレッシヴ・ロック」のファンであれば、“名前は聞いたことがある”という人もいるだろう。花咲く野原で兎に襲いかかる鷲を描いた、印象的なジャケットに見覚えのあるファンもいるかもしれない。しかし彼らの音楽を聞いたことのあるファン、さらに“彼らのアルバムを(LPやCDで)持っているよ”というロック・ファンはかなり少ないのではないかと思うのだ。それほど(特に日本では)フィールズというバンドの知名度は低い(と思う)。
フィールズはグラハム・フィールド(Graham Field)がアンドリュー・マクロック(Andrew McCulloch)とアラン・バリー(Alan Barry)という二人のミュージシャンと共に1971年に結成したバンドだ。一般的にはあまり知られていない人たちだが、当時のプログレッシヴ・ロック・シーンに深い関わりを持っていた人たちだ。中心人物であるグラハム・フィールドはレア・バードのリーダーだった人物だし、アンドリュー・マクロックはキング・クリムゾンのサード・アルバム「リザード」の録音に参加し、さらにマンフレッド・マンやアーサー・ブラウン、さらにEL&Pなどとも一緒に演奏した経験があり、後にはコロシアム解散の後にデイヴ・グリーンスレイドが中心となって結成されたグリーンスレイドに加入することになるミュージシャンだ。アラン・バリーもまたピーター&マイケルのジャイルズ兄弟とバンドを結成していたこともあるらしく、ゴードン・ハスケルのソロ・アルバムにも参加しているという。そうした関連から考えれば“キング・クリムゾン人脈”の中に位置するバンドと言ってよく、結成にあたってはロバート・フリップがグラハム・フィールドに“アドバイスした”ということだから、つまり他の二人のメンバーを紹介、あるいは推薦したのだろう。
結成の経緯から考えても、そしてバンド名の「Fields」から考えても、バンドの中心人物はグラハム・フィールドだろう。彼はキーボード奏者で、この作品でもオルガンやピアノを演奏している。アラン・バリーは基本的にはギタリストで、この作品でもギターとベースを演奏している。アンドリュー・マクロックはドラマーで、楽曲によっては種々の打楽器を演奏しているようだ。彼らによるバンド「Fields」はバンド名をタイトルにしたアルバムを1971年に発表している。収録された楽曲は10曲、トータルで40分ほどのアルバムだ。ほとんどの楽曲はグラハム・フィールドの演奏するキーボードが前面に据えられたもので、音楽的リーダーもグラハム・フィールドであったことが窺える。また「While The Sun Still Shine」と「Fair-Haired Lady」、「The Eagle」の3曲がアラン・バリーの作である以外は、すべての楽曲をグラハム・フィールドが手がけており、曲作りの面でもグラハム・フィールドがバンドの中心であったのだろう。

キーボードを中心にした演奏をベーシスト/ギタリストとドラマーが支えるというトリオ編成のロック・バンドと言えば、やはり真っ先にEL&Pの名を思い浮かべてしまう。EL&Pの他にもクォーターマスやトリアンヴィラートなどの名も思い浮かぶ。またトリオに限定しなければ、グリーンスレイドやアフィニティ、スティル・ライフなどの名も挙げられる。それらのバンドに共通するのは“バンドの主役”としての“リード・ギタリスト”の不在だ。一般的なロック・ミュージックに於いて常にサウンド・メイキングの中心にあった「ギター」という楽器が、これらのバンドでは使われていない、あるいはあくまで“脇役”として使われているに過ぎない。そのことによってそれらのバンドの音楽は他の“一般的な”ロック・ミュージックとは異なる表情を持つことになり、それに対してジャーナリズムやファンは「プログレッシヴ・ロック」の呼称を与えているわけだ。フィールズの音楽もまた、まさにそうしたスタンスに存在する音楽だと言っていい。
その中でフィールズの音楽が特徴的なのは、彼らの音楽が比較的穏やかで牧歌的表情を持っていることだ。キーボード、特にオルガンの演奏を前面に据えた演奏だが、EL&Pやクォーターマスほどハードでアグレッシヴではないし、グリーンスレイドやアフィニティほどジャジーでもなく、トリアンヴィラートほどクラシカルでもない。確かに楽曲によっては“ハード・ロック風”に展開するものもあるし、クラシック音楽の影響の色濃いものもある。少々アヴァンギャルドな雰囲気を携えた楽曲もある。しかしそれらは音楽の“味付け”といった程度のものでしかない。彼らの音楽は、どれほど重厚なオルガンのサウンドが鳴り響いたとしても、その根底には美しいメロディによって紡がれた穏やかな音楽世界が広がっている。彼らの音楽は牧歌的で、少し夢想的で、ほんの少しユーモアがあり、英国的なウィットを感じさせる。いかにも英国のロック・ミュージックだという気がする。そうした音楽性で言えば、プロコル・ハルムの音楽とも共通するものが多いだろう。

アルバムに収録された10曲のうち、「Slow Susan」と「The Eagle」がインストゥルメンタル曲である以外はすべて歌詞を持つ楽曲、すなわち「歌唱」というものを中心にした構成だ。グラハム・フィールドのキーボード演奏は全編を覆い尽くすほどだが、しかしそれでも器楽演奏のみによって成立するような音楽を指向していたのではないように思える。フィールズの音楽は基本的には「歌」を主体とする音楽であり、それを包み込む演奏がオルガンを中心としたロック・ミュージックの意匠を持っているということだ。楽曲そのものもいい。楽曲によってははっとするほど美しいメロディが歌われる。ヴォーカルを担当するのはギタリストのアラン・バリーのようだ。彼の歌唱は決して巧みではないが、良い味があり、良い意味で“アク”がなく、フィールドの音楽世界にうまく溶け込んでいる印象だ。だからフィールズの音楽は、例えばオルガン演奏を主体としたロック・バンドによって演奏されるブリティッシュ・フォークのような味わいもある。
個人的にはやはりグラハム・フィールドのオルガン演奏が響き渡る「A Friend Of Mine」や「While The Sun Still Shine」、「Over And Over Again」といった楽曲が大好きだ。「A Friend Of Mine」ではいきなりEL&P風のイントロが鳴り響いて驚かされるが、聴き進めれば、彼らが単なる“EL&Pフォロワー”ではないことがわかる。打楽器の音を印象的に用いた「Three Minstrels」は少しばかり民俗音楽的な雰囲気もあって面白い。インストゥルメンタル曲である「Slow Susan」は、夢想的な中にほんの少し前衛的な匂いが漂い、アルバム中のアクセントになっている。アラン・バリー作の「Fair-Haired Lady」も印象深い。アラン・バリーの“ギター弾き語り”のように始まり、やがて静かにキーボードが音楽に色彩を与え、静謐で繊細な音楽世界が展開される。同じくアラン・バリー作の「The Eagle」はこのアルバム中で異彩を放つインストゥルメンタル曲だ。クラシック音楽にモチーフを求めた楽曲で、アラン・バリーのギターがフィーチャーされ、効果的にグラハム・フィールドのオルガンやピアノが絡む、ドラマティックな楽曲だ。この「The Eagle」はアルバム収録中で最も一般的な「プログレッシヴ・ロック」の方法論に則った楽曲と言っていい。タイトルとジャケット・デザインの関連を考えれば、アルバムのタイトル・チューンと捉えてよいのかもしれない。収録された楽曲のそれぞれに表情の異なるところはあるが、基本的な音楽の佇まいには共通するものがあり、アルバム全体が散漫になることなく、うまくまとまっているのもいい。

1960年代末から1970年代初頭にかけて、キーボード、特にオルガンの演奏をサウンド・メイキングの中心に据えて音楽を創造するロック・バンドは少なくなかった。バンドによっては完全にギタリスト不在であったり、このフィールズのようにオルガンがメインでギターがサポートという性格のバンドもあり、あるいはギターとキーボードがサウンド・メイキングの両輪となって音楽を創造するものもあったが、共通するのはオルガン演奏がその音楽の創造に果たす役割がとても大きいことだった。そうしたスタイルのロック・ミュージック、すなわちオルガン演奏を堪能できるロック・ミュージックというものを愛するファンというのは実は少なくない。そうしたスタイルのロック・ミュージック、いわば“オルガン・ロック”を愛するファンにとって、フィールズが発表した、このアルバムは、プロコル・ハルムやグリーンスレイドの諸作などとともに愛すべき作品であることは間違いない。
フィールズは結局、このアルバム一枚だけを残して解散、ロック・シーンからその名を消してしまう。そのためか、このアルバムはファンや評論家の間で「幻の一枚」的に扱われることも少なくない。知名度の低さ故か、リイシューされる機会も極めて少ないようで、そのことも「幻の名作」、あるいは「lost masterpiece」などと表現されることの一因になっているのだろう。入手困難な作品ではあるが、“オルガン・ロック”を愛するファンなら何とか入手したい作品だ。「傑作」と呼んでも差し支えない、“オルガン・ロック”を愛するファンの期待に充分に応えてくれる作品である。
This text is written in August, 2011
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.