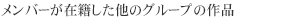Egg
1.Bulb
2.While Growing My Hair
3.I Will Be Absorbed
4.Fugue In D Minor
5.They Laughed When I Sat Down At The Piano...
6.The Song of McGillicudie The Pusillanimous (or Don't Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Celler with Thomas)
7.Boilk
8.Symphony No. 2
-Movement 1
-Movement 2
-Blane
-Movemnet 4
Dave Stewart: organ, piano
Mont Campbell: bass, vocals
Clive Brooks: drums
Produced by EGG
1970 The Decca Record Company Limited
2.While Growing My Hair
3.I Will Be Absorbed
4.Fugue In D Minor
5.They Laughed When I Sat Down At The Piano...
6.The Song of McGillicudie The Pusillanimous (or Don't Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Celler with Thomas)
7.Boilk
8.Symphony No. 2
-Movement 1
-Movement 2
-Blane
-Movemnet 4
Dave Stewart: organ, piano
Mont Campbell: bass, vocals
Clive Brooks: drums
Produced by EGG
1970 The Decca Record Company Limited

以前に発売されたCD(POCD-1843)のライナーに掲載されていたデイヴ・スチュワートの手記によれば、彼は初めはギターを演っていたそうだ。彼は the City of London School に通う学生で、その the City of London School で、後のバンド仲間の二人と出会ったという。一人はヒューゴ・マーティン・モンゴメリー・キャンベル、すなわち Mont Campbell、もう一人がスティーヴ・ヒレッジだ。スティーヴ・ヒレッジはこの頃からすでにギタリストとして卓越していたようで、デイヴによれば“僕の遥か先を行っていた”そうだ。というわけでデイヴはギターを諦め、オルガンへ転向、モント・キャンベルとスティーヴ・ヒレッジの二人にデイヴが加わる形でバンドが出来上がった。ユリエル (Uriel) というバンド名で、もちろん当初はオリジナル曲はなく、クリームやジミ・ヘンドリックス、フリートウッド・マック、そしてナイスなどの曲を演奏していたという。
ユリエル (Uriel) はメロディ・メイカーの広告でイースト・エンダー・クライヴ・ブルックス(つまり Clive Brooks) というドラマーを見つけて四人編成となり、活動を続けてゆくが、やがてスティーヴ・ヒレッジが大学進学のためにバンドを脱退してしまう。新しいギタリストを探してオーディションも行ったようだが、スティーヴ・ヒレッジに代わるギタリストを見つけることはできなかったようだ。その後を知る立場だから言えることだが、スティーヴ・ヒレッジが抜けた穴を埋めるギタリストを見つけることは確かに難しいことだったろう。そのようなわけで以後はデイヴのオルガンを中心としたトリオで活動してゆくことになった。
やがてユリエル (Uriel) は バンド名を「Egg」と改め、Decca Record からのデビューのチャンスを掴む。そうして1970年に発表された Egg のデビュー・アルバムが、バンド名をタイトルにした本作である。

この Egg のデビュー・アルバムには8曲が収録されている。ただ冒頭の「Bulb」はエンジニアのピーター・ギャレンによる効果音的な楽曲で、“演奏時間”も10秒に満たない短いもので、実質的には7曲というべきかもしれない。4曲目に収録された「Fugue In D Minor(フーガニ短調)」はバッハ作曲による人気の高いオルガン曲で、それらを除いた他の楽曲は Egg のメンバー3人の共作となっている。最後に収録された「Symphony No. 2」はそのタイトルからも推測できるが、クラシック音楽に於ける交響曲の形式の組曲で、演奏時間も20分を超える大作だ。そのことからもわかるが、彼らの音楽はクラシック音楽の要素を巧みに取り入れた(前述のデイヴ・スチュワートの手記中の表現を借りれば“盗んだ”)もので、使い古された表現を用いるならば(果たして Egg のメンバーたちがそうしたことを目指していたかどうかは別にしても)“ロックのクラシックの融合”を試みた音楽だということもできる。
このアルバムが発表された1970年、Emerson, Lake & Palmer のデビュー・アルバムが発表された年だ。Emerson, Lake & Palmer の結成以前、キース・エマーソンはナイスというトリオで活動していた。ナイスはまさに“ロックとクラシックの融合”を試みたバンドのひとつだ。デイヴ・スチュワートはそのナイスに多大な影響を受けたようだ。無理はあるまい。オルガン奏者であることに自らの立脚点を見出し、アマチュア・バンドで活動していたデイヴ・スチュワートにとって、オルガンを中心に据えたロック・ミュージックを演奏していたナイスは憧れであり、目標であったのだろう。ユリエル時代にブルース系のロックのコピーに混じってナイスのコピーも行っていたのは、デイヴ・スチュワートの意向だったらしい。スティーヴ・ヒレッジが脱退してギタリストのいないトリオ編成になった後、デイヴ・スチュワートのオルガンを中心にした音楽へ移行してクラシックの要素を取り込んだ音楽を指向するのは当然の成り行きだったろうし、そしてまた、それはデイヴ・スチュワートが音楽的リーダーとなったことを意味するものだろう。

ナイスに影響を受けたデイヴ・スチュワートを中心にした Egg だが、Egg の音楽がナイスと同じ路線のものかと言えば、そうではない。むしろまったく性格の異なる音楽だ。前述したCD(POCD-1843)の解説に、キーボード・マガジンの松中康雄氏は「ナイスがクラシックの要素を半ば強引にロックのビートに乗せて演奏していたのに対して、エッグは実に自然にクラシックを取り入れている」と書かれている。その通りだ。大いに賛同する。僭越を承知で言葉を重ねれば、ナイスの音楽はクラシックの楽曲(あるいは“クラシック音楽”として書かれた楽曲)をロック・ミュージックのダイナミズムの中で演奏することに主眼が置かれていたように思える。キース・エマーソンのそうした姿勢は Emerson, Lake & Palmer にも受け継がれ、傑作「Pictures at an Exhibition」を生むことになるわけだ。ところが、Egg の音楽にはクラシックの楽曲をロック・ミュージックのダイナミズムの中で展開しようという姿勢は見あたらない。そもそも Egg の音楽はロック・ミュージックとしてのダイナミズムに重きが置かれていないのだ。というより、Egg の音楽は果たしてロック・ミュージックなのか、ということだ。
確かに Egg の音楽の基本的な立脚点はロック・ミュージックにあるようだ。しかし、ブルースやロックン・ロールに基盤を持つ、いわば“王道の”ロック・ミュージックとは明らかに異質だ。Egg の音楽がデイヴ・スチュワートのオルガン演奏を主体にしていることにも、その一因はあるだろう。しかしバンドの楽器構成といった表層的な部分より遥かに深いところで、Egg の音楽は大方のロック・ミュージックとは異なる立脚点の上に成り立っている。Egg の音楽は“演奏”のダイナミズムや“表現”としての熱情といったものに主眼を置かず、より前衛に寄って音響的な構築によって成立しているように思うのだ。
Egg の音楽を、例えばローリング・ストーンズの音楽やラモーンズの音楽などと同等の“聴き方”をすると、ひどくわかりにくく退屈なものに聞こえてしまうに違いない。言い方を変えれば、そうしたシンプルでダイレクトなロック・ミュージックを好む人たちには Egg の音楽はおそらく理解してもらえない。Egg の音楽の魅力を理解するためには、彼らの提示する音響的な構築物としての音楽の在り方を、まず受け入れなくてはならない。10秒にも満たない効果音のような「Bulb」や、これも効果音の連なりのような1分ほどの「Bolk」が何故“楽曲”として成立し得るのか。それが理解できなければ、Egg の音楽の魅力は理解できない。
そうした音楽の在り方は、「プログレッシヴ・ロック」と呼ばれる分野の主流の音楽とも異質だ。キング・クリムゾンやイエスといった音楽を愛する人であっても、Egg の音楽に抵抗を示す人は少なくないかもしれない。「プログレッシヴ・ロック」というものの持つ一般的なイメージである幻想性や映像的なイメージ、神話的な物語性といったものを、Egg の音楽からはほとんど感じることができない。“ビッグ・ネーム”のプログレッシヴ・ロックのグループの中に Egg との共通点を敢えて探すとすれば、「A Saucerful Of Secrets」から「The Dark Side Of The Moon」にかけてのピンク・フロイドだろうか。演奏者の意図というものを感じさせずに前衛的な音響的構築物として展開された音楽ということでは通じるものがある。しかしピンク・フロイドはそれをポップの意匠の中に展開して見せたところに真骨頂があった。Egg の音楽はまったく“ポップ”の意匠を身につけようとはしていない。
実は、Egg の音楽に最も近いのは、いわゆるカンタベリー系の一連の音楽である。どこかくぐもったような音像、演奏者の熱情というものを感じさせずにクールに展開する演奏、それでいて知的なスリルを誘う展開、“演奏”なのか“効果音”なのかさえ定かではない音響の連なりの中に浮かび上がってくる音楽として在り方は、カンタベリー・ミュージックとの共通性は少なくない。カンタベリー・ミュージックの多くがそうであるように、変幻自在に表情を変えつつ流れ去る演奏の中に身を浸すようにして感性を委ねたときに初めて、その音楽の魅力は聴き手の前に姿を現すのだ。
Egg 解散の後、デイヴ・スチュワートがやがて Hatfield and the North へ参加、カンタベリー・ミュージックの本流へ合流してゆくのは至極当然のことのように思える。「いやいや、Egg もカンタベリー・ミュージックのグループではないか」と言うファンもいるかもしれない。しかし the City of London School の学生仲間で結成された当時の彼らをカンタベリー・ミュージックのグループと見なすのは無理があるように思える。もちろん後の繋がりから遡って、Egg もカンタベリー・ミュージックの裾野に位置するグループとして捉えることには吝かではないが。

その Egg のデビュー・アルバム、前述の「Bulb」から始まり、ヴォーカル曲の「While Growing My Hair」と「I Will Be Absorbed」が続き、バッハの「Fugue In D Minor」、インストゥルメンタルの「They Laughed When I Sat Down At The Piano...」を挟んでまたヴォーカル曲の「The Song of McGillicudie The Pusillanimous (or Don't Worry James, Your Socks Are Hanging in the Coal Celler with Thomas)」、そしてこれも前述の「Boilk」が続く。ヴォーカル曲は4分から5分ほどの演奏時間だが、他のインストゥルメンタル曲は比較的演奏時間が短い。前述したように効果音のような楽曲もある。ヴォーカル曲と短いインストゥルメンタル曲とを織り交ぜた構成だが、全体の統一感にはまったく破綻がない。すべての楽曲が巧みな整合性を保って融合し合い、通して聴いているとまるで組曲形式のような構成にも聞こえてくる。
そして後半(LP時代のB面)を占めるのが20分超の「Symphony No. 2」だ。その名のように4部構成の大作である。交響曲形式の大作というとイエスの楽曲を思い浮かべるところだが、その味わいはまったく違う。イエスの音楽がクラシック音楽に於けるフル・オーケストラの「交響曲」に相当するものを数人編成のロック・バンドで実現しようとしていたように感じられるのに対し、Egg の音楽は Symphony と名乗りながらもクラシック音楽の交響曲のような壮大なスケール感を実現しようという意志がまるで感じられない。Symphony とは名ばかり、ところどころでクラシックのモチーフが見え隠れするものの、実際には前衛の要素を孕んで展開するジャズ・ロックの組曲と言っていい。

Egg の、このデビュー・アルバムは決して「名盤」と呼ぶに相応しいものではない。1970年発表のアルバムとして、当時のロック・シーンの中でのスタンスを考えてみても、“地味”な作品と言えるだろう。しかし、カンタベリー・ミュージックのファン、特に Hatfield and the North や National Health のファンならぜひとも聴いておきたいアルバムだろう。もちろん、1970年前後に数多く発表された“オルガンを主体としたロック・ミュージック”の好きな人にもお勧めしておきたい。Dave Stewart & Barbara Gaskin の作品を聴いてデイヴ・スチュワートを知ったファンにお勧めできるかどうかは、難しいところだ。
デイヴ・スチュワートというミュージシャンは音楽的素養はどれくらいあったのだろう。前述のCDのライナーにも詳らかでなく、寡聞にしてよく知らないのだが、「Fugue In D Minor」や「They Laughed When I Sat Down At The Piano...」でピアノを演奏し、楽曲の中にクラシックのモチーフを用いていることから考えれば、それなりの素養はあったのだろう。それにしても「They Laughed When I Sat Down At The Piano...」である。英国流のジョーク、というものだろうか。
This text is written in June, 2012
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.