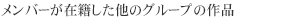一触即発 / 四人囃子
1.(hamabeth)
2.空と雲
3.おまつり(やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった)
4.一触即発
5.ピンポン玉の嘆き
注:一曲目の「(hamabeth)」は本来は発音記号で表記されるタイトルで、ここでは表記不可能なため、推測されるスペリングで代用した
Katsutoshi Morizono : acousthic guitar, electric guitar and vocals.
Hidemi Sakashita : acoustic piano, electric piano, organ, mellotoron and mini moog.
Shinichi Nakamura : bass, pedal bass and backing vocals.
Daiji Okai : drums, air-cymbals, tubularbells and tambarine.
Produced by 四人囃子.
1974 TAM.
2.空と雲
3.おまつり(やっぱりおまつりのある街へ行ったら泣いてしまった)
4.一触即発
5.ピンポン玉の嘆き
注:一曲目の「(hamabeth)」は本来は発音記号で表記されるタイトルで、ここでは表記不可能なため、推測されるスペリングで代用した
Katsutoshi Morizono : acousthic guitar, electric guitar and vocals.
Hidemi Sakashita : acoustic piano, electric piano, organ, mellotoron and mini moog.
Shinichi Nakamura : bass, pedal bass and backing vocals.
Daiji Okai : drums, air-cymbals, tubularbells and tambarine.
Produced by 四人囃子.
1974 TAM.

「四人囃子」という名のロック・バンドの存在を知ったのはいつのことだったろうか。おぼろげな記憶を辿れば、当時の音楽雑誌の片隅に「四人囃子」の紹介記事を見た憶えがある。それによって彼らを知ったのか、あるいは映画化される「二十歳の原点」のサウンドトラックを「四人囃子」が担当するというニュースを知ったのが先だったか、もう記憶が定かではない。いずれにしてもそういったことから考えれば、おそらく1973年頃のことだっただろう。
地方に暮らす身ではレコードが発売される以前に東京周辺で活動するロック・バンドの「音」を知る機会もなく、彼らを紹介する断片的な情報から未だ聴いたことのないその音楽を想像するしかなかった。当時、四人囃子には「和製ピンク・フロイド」といった形容が用いられ、「本格的なプログレッシヴ・ロック」としてのスタンスが強調されていたように思う。「日本のピンク・フロイド」という形容は、ずいぶんと四人囃子に対するイメージを膨らませてくれたものだった。そしてまた「四人囃子」というその名が良かった。英単語ではなく日本語を用いたバンド名、もちろん「○○○○・バンド」や「○○○○ズ」といった名ではなく、さらに「囃子」という言葉が、象徴的だった。その語感は、欧米のロックの模倣ではない日本のロックだという主張にも感じられて、心惹かれたものだった。
やがて1974年の夏前、四人囃子の実質的なデビュー・アルバム「一触即発」が発表された。ある時、ラジオ番組で「空と雲」を聴いた。その時の衝撃は言葉にならない。その音楽は想像と期待を遙かに超えたものだった。地方の町の小さなレコード店に「一触即発」を注文した。月々の小遣いをやりくりしてLPレコードを購入していた当時としては、きちんと聴いたこともないバンドのレコードを購入するというのは、ひとつの「賭け」だった。しかし「賭け」に勝つ自信があった。四人囃子というバンドの「一触即発」というデビュー・アルバムは希にみる傑作なのだという、不思議な確信があった。そしてそれは間違っていなかった。
「一触即発」は素晴らしかった。何度も何度も繰り返し聴いた。真っ黒なレコード盤に封じ込められた「宝物」を手に入れたのだという喜びがあった。あれから30年ほどが経ち、「宝物」の容れ物はLPレコードからCDへと変わったが、今も手元に置かれ、ときおりプレーヤーのトレイに収まる。聞こえてくる音楽にあの頃の空気を思い出しはするが、音楽そのものは決して懐古趣味的なものに陥ることがない。その音楽は幾多の月日を経た今でも充分に新鮮で、「宝物」の輝きは色褪せることがない。

1973年から1975年くらいにかけての時期、英国で「ハード・ロック」や「プログレッシヴ・ロック」が、そして米国では「サザン・ロック」や「ウエスト・コースト・サウンド」が隆盛を迎えていた頃だった。日本では1960年代末期のグループ・サウンズの狂騒も醒めて、ロックはようやく黎明期から発展期へと移り変わろうとしていた時期だった。しかし当時の日本ではロック・ミュージックは今から考える以上にアンダーグラウンドな、マイナーな存在でしかなかった。「若者の音楽」の主流はフォークであり、吉田拓郎や井上陽水といったシンガーたちが圧倒的な人気を誇っていた。当時、「ロック・バンド」として一般に認知されていたのは1972年にデビューしたキャロルくらいのものだったのではないか。そうした状況に苦笑いしながら、欧米のロック・ミュージックを好んだ者たちは自分たちの耳にも応えてくれる「本格的な」ロック・バンドの登場を待ち望んでいたのだ。
そのような中、1972年にサディスティック・ミカ・バンドが、1973年にはコスモス・ファクトリーがデビューし、さらに1975年にはクリエイションとカルメン・マキ&OZのファースト・アルバムが発表され、特にブリティッシュ系のロックを好むファンにとって、ようやく日本のロック・シーンが期待に応えてくれそうな状況になりつつあった。四人囃子はそうしたバンドたちと共に迎えられたのだ。
「一触即発」は、当時の日本のロック・シーンに大きな衝撃を与えた作品だった。「日本人にロックがやれるのか」とか「日本人のロックは英語で歌うべきか日本語で歌うべきか」といった陳腐なテーマが真面目に論じられていた時代から、まだわずかな年月しか経ってはいなかったのだ。多くのミュージシャンたちが試行錯誤を繰り返す中からようやくそれなりの道筋を見つけていこうとしていた時代だった。四人囃子の「一触即発」はそうした混沌から一気に浮上した。ある意味では、四人囃子の登場と「一触即発」の発表はまさに「日本のロック」の提示だった。前衛的なプログレッシヴ・ロックのイディオムを内包しつつ、ハードに展開するロック・サウンド、透明感のあるその音世界とシュールな日本語歌詞とが見事に呼応する様は、当時の日本のロック・シーンに於いて無類のものだった。デビュー・アルバムを発表したばかりの四人囃子は、しかしこの傑作によって即座に日本のロック・シーンの頂点の一角に登り詰め、以後コスモス・ファクトリーと共に「日本の二大プログレッシヴ・バンド」として1970年代日本ロック・シーンに君臨することになる。

例えば夏の日の夕暮れが迫る頃、見慣れた風景の中に奇妙な違和感を覚えたことはないか。どこからか蜩の声が聞こえ、川向こうの鎮守の森が残照に浮かぶ時刻、目の前の日常が現実味を失って曖昧に溶けてゆくような、そんな漠然とした不安を感じたことはないか。軒先の風鈴がぴくりとも動かなくなった夕凪の中、家族の顔がまるで見知らぬ人間のように思えたことはないか。神社の鳥居や、路地裏で遊ぶ子どもたちの声や、風に乗って聞こえる祭囃子や、酸漿の赤い色に、不思議な既視感を誘われたことはないか。ありふれた日常の中に潜む危うい非日常の姿を覗き見てしまったような、拠り所のない孤独感を感じたことはないか。
「一触即発」の音楽世界が喚起するのは、そうしたイメージだ。透明感のあるサウンドとシュールで象徴的な歌詞は互いに呼応して、聴き手の前に日常の現実からわずかにずれた異世界を現出する。青く澄んだ夏空が暗く墜ちるような、午後の陽射しに照らされた街路の明暗が反転するような、現実から剥離してゆく不安な感覚。それは「現実」というものの脆弱さを晒し、「日常」というものが孕む不条理を描き出す。
その音楽が聴き手に与えるそうした印象は、確かにピンク・フロイドの音楽と同質のものであるかもしれない。しかし「一触即発」がそうした欧米のロック・ミュージックの単なる模倣に終わることなく独自性を確立している背景には、その音楽が極めて日本的な感性に満ち、日本的な情景をイメージさせる点にある。
「一触即発」がもたらす日本的な情景は、その歌詞世界の印象に依るところも大きい。シュールな歌詞世界が描き出す幻惑的な心象風景は、同じ日本に生まれ育った者同士が共有する、微妙な空気感に満たされている。シュールな歌詞の内容は、聴く者によってどのようにも解釈することを許す。言葉遊びのように綴られる歌詞は、深読みすれば少年期に感じる漠然とした不安感や疎外感を表現しているようにも見えるが、安易な解釈を超えて言葉そのものが象徴的な意味を持って独立している。その歌詞世界は「一触即発」の音楽世界を決定づける上で大きな役割を果たしており、その意味で詩作を担当した末松康生は四人囃子の五人目のメンバーであったと言っても過言ではない。
そして四人囃子の演奏は、その歌詞世界と見事に呼応し、歌詞の描く世界を「音」として表現することに成功している。クールな感触を伴いながら透明感に溢れた音像の印象は、繊細な中にも緊張感に満ちており、歌詞に歌われる言葉と同等な雄弁さで聴き手の意識に迫る。歌詞の言葉と音の響きは互いに呼応して、聴き手の記憶の中に忍び込み、聴き手の中に眠る懐かしい風景を拾い上げ、忘れていた幼い日の不安を呼び覚ます。聴き手の意識の隙間に入り込み、現実と非現実の狭間に漂うような浮遊感を誘う。この音楽の持つそうした印象こそが、この作品を「プログレッシヴ・ロック」として成立させているのだ。

日本的な情感に満ちた世界を創造しつつ、「一触即発」はしかし「日本のロック」であることに甘んじていない。その演奏はあくまでテクニカルにアグレッシヴにロック・ミュージックの「核」に真正面から切り込んでゆく。確かにそこにはピンク・フロイド的な手法も取り込まれてはいるが、この音楽の基本はあくまでハードでアグレッシヴな「ロック」だ。その演奏は痛快で「かっこよく」、聴く者にある種のカタルシスさえもたらしてくれる。特に「おまつり」や「一触即発」などで聴かれるハードな演奏は、当時の欧米のロックにも決して劣ることのない「ハード・ロック」と言えるだろう。
四人囃子の演奏の魅力は、やはり森園勝敏のギター・プレイの魅力に依るところが大きい。クリアで繊細なサウンドからディストーションの効いたアグレッシヴで豪快なサウンドまで、森園は変幻自在にロック・ミュージックの王道を奏でてゆく。そしてまた坂下秀美のキーボード、特にエレクトリック・ピアノの音色が、この作品の根底に流れる色彩を決定している。もちろんベースの中村真一とドラムスの岡井大二の演奏もまた、「一触即発」の世界になくてはならない独特の魅力を持っている。ヴォーカルを担当するのはギターの森園で、当時「誰も歌わなかったから仕方なく自分で歌った」のだそうだが、彼のヴォーカルを好むファンも多い。決して巧みとは言い難い歌唱だが、独特の「味」があり、声質も「一触即発」の世界によく似合って魅力的だ。「おまつり」のエンディング部で聴かれるパーカッションは、当時「頭脳警察」のメンバーだったトシの客演である。当時彼らは仲が良かったらしく、1973年10月に行われた日比谷野音での「聖ロック祭」の頭脳警察のステージではレコード・デビュー前の四人囃子がバックを担当している。
四人囃子の演奏は、やはり「日本人の血」というものなのか、欧米のミュージシャンには無い感性を感じさせる。虫の声や風のそよぎといった自然音に音楽的な魅力を感じ、それを愛でるという感性は日本人独特のものだという話を聞いたことがあるが、「一触即発」の音楽世界の根底にはそうした感性が深く浸透している気がする。演奏自体の持つクールな透明感、そして演奏の随所に見られる微妙な「間」(あくまで「間」であって決して「タメ」ではない)の在り方もまた日本的な感性と言ってよいのかもしれない。それは「わび・さび」と称される感覚にも似ているのではないか。その感性の在り方が、四人囃子とピンク・フロイドを決定的に隔てている。「ピンポン玉の嘆き」のイントロで聴かれるピンポン玉の弾む音と、「タイム」のイントロで聴かれる時計の音とは、似たような方法論でありつつ、その音のもたらす音楽的効果は全く異なったものだ。
そのような感性に裏付けられつつ、彼らは欧米で生まれたロック・ミュージックを自らの中に昇華し、自らのものとして表現する。作品世界の根底に日本的感性が脈打っていることは、作品の制作にあたって意識的に行われたことではあるまい。そうしたことが意図的に行われる時、ややもすれば「あざとく」感じられ、音楽自体を浅薄なものに貶めてしまう危険性を伴うものだが、「一触即発」にはそうした浅薄さは微塵も感じられない。そこにあるのは「日本的なロック」を造ろうとした結果ではなく、才能に溢れた四人の若い日本人ミュージシャンが自らの表現欲求に従って真摯にロック・ミュージックの創造に向き合った所産だ。それ故に、「一触即発」は当時も第一級の「ロック・アルバム」としての評価を勝ち得たのであり、現在も時代の変遷に風化して陳腐化することのない傑作として残るのだ。

「一触即発」の後、ベースの中村真一が四人囃子を脱退する。バンドはベースの佐久間正英を迎えて再出発、シングル「空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ」と、これも傑作とされるアルバム「ゴールデン・ピクニックス」を発表するが、その後には森園勝敏が脱退することになる。メンバー・チェンジとともに音楽性も変化していった四人囃子だが、「一触即発」と「空飛ぶ円盤に弟が乗ったよ」との間でさえ、やはりその音楽世界の在り方が決定的に違っている。バンドとしての方針であったのだろうが、やはりメンバーが交替したことによる演奏そのもの印象の違いも無視できない要因であるだろう。「一触即発」に先立つ「二十歳の原点」が映画用に制作された変則的な作品であることを考えれば、オリジナル・メンバーによる「四人囃子」は正式なアルバム作品として唯一この「一触即発」だけを残したことになる。黎明期の日本ロック・シーンが残した、まさに奇跡的な至宝である。
1970年代に発売されたLPレコードは後に廃盤となり、CD時代になって復刻されるまで、「一触即発」はマニアの間の垂涎の的であったという。日本のファンのみでなく、海外の「プログレッシヴ・ロック」マニアの注目も集め、中古レコードは高値で取り引きされたのだという。海外のロック・ファンに「一触即発」がどのように解釈されたのかは知らない。「一触即発」の中に感じられる日本的情緒感も、海外のファンにはまた違った印象をもたらしたことだろう。
「日本のピンク・フロイド」などと形容され、1970年代の「日本プログレッシヴ・ロック」の代表的バンドのように語られる四人囃子だが、その音楽は当時の「プログレッシヴ・ロック」や「ハード・ロック」といった便宜的なジャンルを遙かに超えている。そうした「ジャンル」の概念だけが独立して先行してゆく以前の、すべての「ロック」が必然的にハードでアグレッシヴでプログレッシヴであった時代の、これは日本に於けるロック・ミュージックの理想的な結晶のひとつである。
This text is written in July, 2002
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.