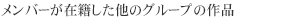When The Raven Has Come To The Earth / Strawberry Path (Jimmy & Hiro)
1.I Gotta See My Gypsy Woman
2.Woman Called Yellow "Z"
3.The Second Fate
4.Five More Pennies
5.Maximum Speed Of Muji Bird (45 seconds of schizophrenic sabbath)
6.Leave Me Woman
7.Mary Jane On My Mind
8.Spherical Illusion
9.When The Raven Has Come To The Earth
Shigeru Narumo : guitar, acoustic guitar, hammond organ, piano, bass, backing vocal, composition & arrangement, produce
Hiro Tsunoda : drums, percussion, lead vocal, backing vocal, composition & arrangement
Guests:
Isao Eto : bass (1,3,6,7,8,9)
George Yanagi : vocal (1)
Nozomu Nakatani : flute (9)
Masahiko Aoi : strings & chorus arrangement (7)
Produced by Masaharu Honjo, Shigeru Narumo, Tadataka Watanabe
1971 Nippon Phonogram
2.Woman Called Yellow "Z"
3.The Second Fate
4.Five More Pennies
5.Maximum Speed Of Muji Bird (45 seconds of schizophrenic sabbath)
6.Leave Me Woman
7.Mary Jane On My Mind
8.Spherical Illusion
9.When The Raven Has Come To The Earth
Shigeru Narumo : guitar, acoustic guitar, hammond organ, piano, bass, backing vocal, composition & arrangement, produce
Hiro Tsunoda : drums, percussion, lead vocal, backing vocal, composition & arrangement
Guests:
Isao Eto : bass (1,3,6,7,8,9)
George Yanagi : vocal (1)
Nozomu Nakatani : flute (9)
Masahiko Aoi : strings & chorus arrangement (7)
Produced by Masaharu Honjo, Shigeru Narumo, Tadataka Watanabe
1971 Nippon Phonogram

「メリー・ジェーン」という楽曲をご存じだろうか。甘美で感傷的なメロディを持つスロー・バラードで、正式な曲名を「Mary Jane On My Mind」という。オリジナルを歌っているのは1960年代からドラマー/シンガー/コンポーザーとして活動するつのだひろで、作曲もつのだ本人による。1970年代後半のディスコ・ブームのときには、「メリー・ジェーン」はサンタナの「君に捧げるサンバ」などと並んで「チークタイム」で使用される定番の楽曲だったから、それで耳にした人も少なくないだろう。その後もさまざまな場面で耳にする機会が多く、誰でも一度は聞いたことがあるのではないかと思えるほどの有名曲だ。ではその「メリー・ジェーン」が初めてレコード盤に刻まれて世に発表されたのがいつなのか、知っている人は案外少ないのではないだろうか。「メリー・ジェーン」という楽曲は、そもそもはつのだひろが成毛滋と組んだロック・ユニット「ストロベリー・パス」が1971年に発表したアルバム「大烏が地球にやってきた日」の収録曲だった。後年になってつのだひろ自身が再演したヴァージョンもあるが、このアルバムに収録されたヴァージョンこそが「オリジナル」と言っていい。

成毛滋は1960年代にはザ・フィンガーズのメンバーだった。ザ・フィンガーズは当初はいわゆる「エレキ・インスト」のバンドで、成毛はザ・フィンガーズ在籍時にエレクトリック・ギターとオルガンの演奏技術を身に付けていったようだ。ザ・フィンガーズは1960年代の「グループサウンズ」ブームの波に揉まれながら活動を続け、その終焉と共に1969年に解散したが、成毛は最後までそのメンバーで、最終期にはバンド名を変えてクリームやディープ・パープルといった欧米のロックをカヴァーしていたらしい。ザ・フィンガーズはメンバーの変遷も多かった。初期には高橋幸宏の兄である高橋信之もザ・フィンガーズに在籍していたという。途中でメンバーとなったアメリカ育ちの蓮見不二男(Christopher Lynn)はザ・フィンガーズ解散後も成毛滋の活動に深く関与している。余談だが、若き日の荒井由実がザ・フィンガーズの後期のメンバー、香港出身のシー・ユー・チェンのいわゆる「追っかけ」をしており、そのシー・ユーが他ならぬ「Yuming」という愛称の名付け親だという逸話はファンにはよく知られている。
つのだひろは、本名を「角田博民」といい、漫画家のつのだじろうを兄に持つ。ドラムを始めたのは中学時代らしいが、天賦の才に恵まれていたのだろう、高校時代にはプロとして活動を始め、ジャズ、ロック、フォークと、そのスタイルを問わず、さまざまなミュージシャンのバックでそのテクニカルでパワフルな演奏を披露している。時代が1970年代を迎えた頃、つのだと成毛滋は当時ゴールデン・カップスのメンバーだった柳ジョージと共に、ジプシー・アイズを結成する。その演奏は当時かなりの人気だったようだが、残念ながら正式な音源が残されていない。成毛滋、つのだひろ、柳ジョージのトリオ編成のジプシー・アイズだったが、当時渡辺貞夫のカルテットに加入していたつのだひろもゴールデン・カップスの柳ジョージもそれぞれに多忙だったため、演奏時のメンバーは流動的だったという。柳ジョージが参加できないときは必然的に成毛滋とつのだひろのふたりだけになった。すなわち、この柳ジョージの参加していないジプシー・アイズが、そのままストロベリー・パスへと移行する。

1969年から1971年にかけての頃、1960年代後半に一大ブームを迎えた「グループサウンズ」の狂騒も終焉を迎え、日本の音楽シーンはその余韻の中で「日本のロック」を生み出そうともがいていた。ゴールデン・カップスは「グループサウンズ」の歌謡曲的意匠をかなぐり捨て、ロック・バンドに変貌していた。ダイナマイツの山口冨士夫は1969年に村八分を結成、その過激なライヴが話題となっていた。491のジョー山中、ビーバーズの石間秀樹、フラワーズの和田ジョージ、タックスマンの上月ジュンは1970年にフラワー・トラヴェリン・バンドを結成、欧米のロック曲のカヴァーによるデビュー・アルバムを発表した。スパイダースの井上堯之、大野克夫、タイガースの沢田研二、岸部一徳、テンプターズの萩原健一、大口広司の六人は本格的なロック・バンドを目指して1971年にPYGを結成、GSのスターが集結したバンドは「スーパー・グループ」と呼ばれた。
しかし当時の日本の音楽シーンで「ロック」はまだまだアンダーグラウンドな存在でしかなかった。「ロック」はまだ遠い海の彼方の音楽だった。「グループサウンズ」の一大ブームに沸いた音楽業界も、「グループサウンズ」を日本に於ける「ロック」の萌芽とは見なしていなかったろう。ビートルズやローリング・ストーンズに憧れてバンドを結成した若者たちは、デビューするや否やレコード会社の用意した歌謡曲を歌わされた。大手のレコード会社にとって「グループサウンズ」は海外のポップスを真似た「アイドル歌謡」でしかなかったに違いない。クリームやレッド・ツェッペリン、キング・クリムゾンの登場などによって欧米のロック・ミュージックが新たな局面を迎えるのと呼応するように、日本でも「グループサウンズ」の残り火の中から「ロック」が生まれ出ようとしていたが、当時の日本の音楽業界はその音楽を理解できなかった。そのような時代にも幾つかのロック・アルバムが制作、発表されたが、それらは奇跡的な幸運に恵まれていたのだと言えるかもしれない。
ストロベリー・パスの「大烏が地球にやってきた日」は、そのような奇跡的幸運に恵まれて発表されたロック・アルバムの中のひとつだ。成毛滋は欧米のロックと同等のものを目指していた。楽曲はすべて英語詞だった。歌詞はすべて蓮見不二男(名義は「Christopher Lynn」)が書いた。そのロックは英国のハード・ロックやプログレッシヴ・ロックを強く意識したものだった。と言うより、彼らはまさに「ブリティッシュ・ロック」を、演奏したのだ。

成毛滋はギターとハモンドを演奏し、つのだひろはドラムを叩き、そして歌った。ベースは江藤勲がサポートした。ストロベリー・パスの「大烏が地球にやってきた日」に於いて、彼らは当時のブリティッシュ・ロックそのものを演奏している。成毛のギターもハモンドも当時のブリティッシュ・ロックの匂いを濃厚に纏っている。当時の日本ロック・シーンにこれほどの演奏を聞かせるミュージシャンがいたことにまず驚く。
冒頭に収録された「I Gotta See My Gypsy Woman」のみ、ヴォーカルに柳ジョージが参加している。成毛滋とつのだひろによるストロベリー・パスにゴールデン・カップスの柳ジョージがゲスト参加している、という記述を見ることもある。それも間違いではないが、「I Gotta See My Gypsy Woman」に於ける編成こそが他ならぬジプシー・アイズそのものであり、当時の成毛滋のやりたかった本来のスタイルであるに違いない。つのだひろの歌唱も巧みで味があって素晴らしいものだが、当時のストロベリー・パスの(あるいはジプシー・アイズの、または成毛滋の、と言ってもいい)スタイルには柳ジョージのヴォーカルが似合っている。ハマっている、という言い方が相応しいかもしれない。柳ジョージのヴォーカル、つのだひろのドラム、そして成毛滋のギターで聞かせる「I Gotta See My Gypsy Woman」こそ、このアルバムの白眉だと言っていい。その演奏は当時のブリティッシュ・ハード・ロックそのものだ。何も知らずに聞けば1970年代の英国のバンドの演奏だと思ってしまうだろう。
「I Gotta See My Gypsy Woman」、「Woman Called Yellow "Z"」、「Five More Pennies」、「Leave Me Woman」は蓮見不二男(Christopher Lynn)が歌詞を書き、成毛滋が曲を書いた。「I Gotta See My Gypsy Woman」以外はつのだひろがヴォーカルを担当しているが、演奏のスタイルは「I Gotta See My Gypsy Woman」と同様のブリティッシュ・ハード・ロックだ。成毛滋のギターとハモンド、つのだひろのドラムを存分に堪能することができる。
「The Second Fate」はつのだひろ作曲によるインストゥルメンタル曲で、プロコル・ハルムの「青い影」を彷彿とさせるようなオルガンの演奏が印象的なスロー・ナンバーだ。「Mary Jane On My Mind」は本稿冒頭で書いたが、蓮見不二男(Christopher Lynn)作詞、つのだひろ作曲の超有名曲だ。この曲のみ女性コーラスやストリングスが加えられたアレンジで、「ロック」というよりはヨーロピアン・ポップスのような表情を見せる。このアルバムの中ではあまりに他の楽曲と印象が異なり、整合感に欠けるのが難点だが、やはり名曲、聴き応えは充分だ。
「Maximum Speed Of Muji Bird」は成毛滋作曲による1分足らずの小品で、クラシカルな印象のオルガン演奏のみの楽曲だ。日本語でのタイトルとされた副題「45 seconds of schizophrenic sabbath(45秒間の分裂症的安息日)」というのが、今から思えばなかなか微笑ましい。「Spherical Illusion」は成毛滋とつのだひろの共作によるインストゥルメンタル曲で、ヘヴィなギター・リフが印象的なハード・ロックだが、中盤ではつのだひろのドラムソロが繰り広げられている。楽曲として完成されているものではなく、ジャム・セッション風にふたりの演奏をレコーディングしたものかもしれない。
アルバムのタイトル・トラックである「When The Raven Has Come To The Earth」は、成毛滋作曲のインストゥルメンタル曲だ。フルート演奏を前面に据えたスロー・ナンバーで、風の音や鳥の羽ばたきの音といったエフェクトも使用するなど、「プログレッシヴ・ロック」のイディオムに彩られた楽曲だ。アコースティック・ギターを使用した静かな演奏からやがてエレクトリック・ギターが響き渡り、劇的な構成を見せる。何やら不穏で不吉な印象の、世界の終焉を感じさせるような印象の楽曲で、聴き応え充分、このアルバムのタイトル・トラックに相応しいものだ。
アルバムは全体の構成や密度、各楽曲そのもののクオリティといったさまざまな点に於いて、やはりまだまだその水準は高くはないと認めざるを得ない。録音の音質も良くない。しかし彼らの歌と演奏そのものは、充分に魅力的なものだ。1971年に発表された日本人によるロック・アルバムとして、これほど完璧に「ブリティッシュ・ロック」のイディオムに基づいた演奏があったということがひとつの驚きに値するのではないか。そしてさらに言えば、このアルバムの演奏そのものの魅力には「1971年に発表された日本人によるロック・アルバムにしては」という前置きは不要だ。成毛滋とつのだひろの演奏そのものが、熱を帯びた「ロック」の匂いを放っている。
このような「ブリティッシュ・ロック」のスタイルの日本人によるロック・ミュージックに対して、「英国のロックの模倣に過ぎないではないか」という意見もあった。確かに模倣であるかもしれない。しかし、模倣で良いではないか。この模倣は、決して志を欠いたモノマネや悪意ある盗用ではない。欧米のロックに対する敬愛と支持と共感と憧憬に満ちた模倣だ。演奏技法や楽曲の構成といった表層的なものをただ真似ているのではない。「ロック・ミュージック」というものの本質的で根元的な「在り方」を、自らの音楽でも実現しようとするための模倣だ。そしてそこから、やがてオリジナリティというものが育ってゆくのだ。

成毛滋とつのだひろによるストロベリー・パスは、この後エスケープというバンドのギタリストだった高中正義をベーシストとして加えてトリオ編成となり、フライド・エッグと名を変えて活動を継続する。フライド・エッグは2枚のアルバムを残し、その1枚目のアルバムは「日本初のプログレッシヴ・ロック」と評されることもある。フライド・エッグは日本ロック黎明期の重要バンドのひとつとして語られることも少なくないが、それに先立つストロベリー・パスは、あまりその名を目にする機会が少ないような気もする。それが少し残念だ。
ストロベリー・パスのアルバム「大烏が地球にやってきた日(When The Raven Has Come To The Earth)」は、お世辞にも「名盤」とか「傑作」と呼べるような作品ではない。しかし日本の音楽シーンが「グループサウンズ」の狂騒の余韻の中で必死になって本物の「ロック」を生み出そうとしていた時代に発表されたロック・アルバムとして、そしてまた成毛滋というミュージシャンが若い日に残した作品のひとつとして、ロック・ファンには無視できない作品と言っていい。日本ロックのファンはもちろんだが、むしろ1970年代初頭のブリティッシュ・ロックを愛するファンにこそ、聴いて欲しい。日本人ミュージシャンによって日本で作られたロック・アルバムだが、このアルバムに収録された演奏は1960年代末から1970年代初頭にかけての「ブリティッシュ・ロック」そのものだからだ。
ちなみにアルバム・ジャケットのイラストを描いたのは「サイボーグ009」や「仮面ライダー」の原作者として知られる石森章太郎だ。ライナーは成毛滋の友人である景山民夫が書いている。作品内容にはまったく触れられておらず、とてもライナーと呼べるものではないが、景山民夫のファンであれば無視できないものかもしれない。またアルバムの日本語タイトル「大烏が地球にやってきた日」は希に「大鳥が地球にやってきた日」と誤記されているものを見ることがあるが、英語タイトルが「When The Raven Has Come To The Earth」となっていることからもわかるように「鳥(とり)」ではなく「烏(からす)」である。「raven」は日本ではワタリガラス(渡り烏)、あるいはオオガラス(大烏)と呼ばれる大型のカラスのことで、欧米でカラスというと通常はこの種を指す。日本でもカラスはあまり良いイメージではないが、「raven」もまた不吉な鳥とされているようだ。「When The Raven Has Come To The Earth」の楽曲の持つイメージは、荒涼とした終末世界に羽ばたく巨大なワタリガラスの姿といったところだろうか。
This text is written in January, 2007
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.