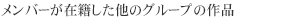In The Court Of The Crimson King / King Crimson
1.21st Century Schizoid Man including Mirros
2.I Talk To The Wind
3.Epitaph including March For No Reason and Tomorrow And Tomorrow
4.Moonchild including The Dream and The Illusion
5.The Court Of The Crimson King including The Return Of The Fire Witch and The Dance Of The Puppets
Robert Fripp - guitar.
Ian McDonald - reeds, woodwind, vibes, keyboards, mellotron & vocals.
Greg Lake - bass guitar & lead vocals.
Michael Giles - drums, percussion & vocals.
Peter Sinfield - words & illumination.
Produced by King Crimson.
1969 E.G. Records Ltd.
2.I Talk To The Wind
3.Epitaph including March For No Reason and Tomorrow And Tomorrow
4.Moonchild including The Dream and The Illusion
5.The Court Of The Crimson King including The Return Of The Fire Witch and The Dance Of The Puppets
Robert Fripp - guitar.
Ian McDonald - reeds, woodwind, vibes, keyboards, mellotron & vocals.
Greg Lake - bass guitar & lead vocals.
Michael Giles - drums, percussion & vocals.
Peter Sinfield - words & illumination.
Produced by King Crimson.
1969 E.G. Records Ltd.

「鑑賞し、評論することを許した最初のロック・ミュージック」という表現を、以前誰かが使っていたような記憶がある。その言葉が「クリムゾン・キングの宮殿」という作品のことを指して使われていたのか、あるいは「プログレッシヴ・ロック」と呼ばれたスタイルのロック・ミュージックの総体を指していたのかは失念してしまった。もしかしたらまったく別の作品を指して使用された言葉だったかもしれない。
しかしその表現だけは見事に脳裏に刻み込まれ、そのイメージは「クリムゾン・キングの宮殿」という作品のイメージと呼応して今に至っている。これほど「クリムゾン・キングの宮殿」の革新性を見事に的確に表現する言葉は他にないのではないか。

1950年代に「ロックン・ロール」として産声を上げて以来、ロック・ミュージックは猥雑で野卑な音楽と見なされてきた。テレビ番組に出演したエルヴィス・プレスリーが、「腰の動きが卑猥だ」というので、胸元から上だけを放映されたという逸話は有名だ。ビートルズでさえ「長髪」の不良グループであったし、その音楽はただうるさいだけで、「良識ある大人たち」からは「音楽」とさえ見なされなかった。
ロックン・ロール以来、ロック・ミュージックは基本的にダンス・ミュージックだった。肉感的なリズムで若者にアピールするだけの、低俗な流行音楽でしかなかった。1960年代後半になってロック・ミュージックがカウンター・カルチャー的意味合いを帯びるようになっても、それはそれでまた「大人たち」が眉をひそめる対象となってしまった。ビートルズをはじめとする何組かのアーティストたちがさまざまな手法で「音楽的」成果を上げていた頃にも、未だロック・ミュージックは芸術性とは無縁の、「音楽」の「蚊帳の外」であり続けた。
そうして1969年、「クリムゾン・キングの宮殿」が発表されたのだった。ロック・ミュージックが潜在的に持っている暴力性や革新性を携え、美と芸術性を纏って、圧倒的な完成度でその作品はロック・シーンに提示されたのだ。それはひとつの革新であっただろう。当時のロック・ミュージックが探し求めていた「新しい在り方」のひとつを、この作品は見事に具現化し、「芸術」としてのロック・ミュージックの可能性を示唆して見せたのに違いない。
もちろんこの作品をきっかけにそれまでのロック・ミュージックに対する一般の認識が一変したということはないし、以後のロック・ミュージックがすべて「芸術」としての方向を目指したというわけではない。しかし少なくともこの作品が示して見せた可能性はロック・ミュージックの未来のひとつであったし、何よりロック・ミュージックを「芸術」の一分野として解釈し、それを「鑑賞」し、「評論」するに値する対象としてもよいのだという考え方を明確にし、そうした考え方の象徴のひとつに成り得たのは事実だっただろう。

日本のファンの間で「宮殿」と短く呼称されることの多い「In The Court Of The Crimson King(クリムゾン・キングの宮殿)」は、いわゆる「プログレッシヴ・ロック」の代表作のひとつであるように見なされる。「プログレッシヴ・ロック」のアーティストの中で最も成功し、人気を得たグループのひとつであるキング・クリムゾンの、デビュー作にしておそらく最高傑作であるこの作品は、「プログレッシヴ・ロックの代表作」としての名に恥じることはない。
この作品が発表された当時、「プログレッシヴ・ロック」は未だその名も概念も存在してはいなかった。1960年代の終わり頃から見られた革新的な音楽性を持つ一連のロック・ミュージックは、欧米では「アート・ロック」と呼称されることもあり、「宮殿」もまたそうしたロック・ミュージックのひとつと見なされていた。1970年代に入ってピンク・フロイドによる実験性溢れる作品群やイエスの宇宙的広がりを感じさせる音楽が発表され、さらにキング・クリムゾンを抜けたグレッグ・レイクらによって結成されたEL&Pによるアグレッシヴで先進的なロック・ミュージックなどが次々に提示され、それらがロック・シーンで大きな人気を得るに至って、それらを共通する「ジャンル」として扱う見方が生じ、その「ジャンル」に対して「プログレッシヴ・ロック」の名が与えられたのだ。
「宮殿」は時に「プログレッシヴ・ロック」の誕生を告げた作品として見なされることもある。確かにこの作品以後のロック・シーンの傾向やこの作品がロック・シーンに与えた影響の大きさを考えれば、そうした解釈も正しいものだろう。後期のビートルズやムーディー・ブルースの音楽などにも、「プログレッシヴ・ロック」の呼称が相応しいものがあるが、やはりそれは一種の「萌芽」でしかなかっただろう。後に「プログレッシヴ・ロック」と呼ばれるようになるロック・ミュージックのスタイルと思想は、まさに「クリムゾン・キングの宮殿」という作品によって明確に具現化し、ロック・ファンの前に大きな衝撃を伴って提示されたのだ。

「クリムゾン・キングの宮殿」は、その後「プログレッシヴ・ロック」というスタイルのロック・ミュージックに対して用いられるようになる形容のすべてを内包している。「幻想的」、「神秘的」、「叙情的」、「物語的」、「先進的」、「前衛的」、そうした言葉で形容される「プログレッシヴ・ロック」の魅力のすべてを、この作品は持っている。この作品が聴き手に喚起させる心象風景こそは、後に「プログレッシヴ・ロック」と呼ばれるようになるスタイルのロック・ミュージックが共通して持つ魅力の象徴であるだろう。
かすかに響くノイズのような音に先導されて始まる「21st Century Schizoid Man」の、その暴力的なまでの演奏は鑑賞者に大きな衝撃をもたらす。歪んだ歌声もまた内に潜む狂気的なものを象徴するかのようだ。そこから一転して静寂をもたらす「I Talk To The Wind」、その穏やかな印象もひときわ心を惹きつける。そして哀感に満ちた「Epitaph」、物悲しい響きは忘れ去られた哀しみを甦らせてくれるようでもある。「Moonchild」は幻想的な表情が魅力的な楽曲だ。「including The Dream and The Illusion」とあるように、その後半部の演奏は夢と幻の中に漂うような心象を描く。そして最後を締めくくる「The Court Of The Crimson King」、この作品の持つ魅力をすべて統合したかのような構成と、一編の物語を想起させるような印象が見事だ。まるで夢想の霧がどこかへ吸い込まれて消えてしまうような楽曲の終わりも素晴らしい。
それぞれに異なった印象を与えてくれる楽曲が並ぶが、決して散漫になることなく、より大きなテーマの元に統合された統一感をもって、鑑賞者の前に作品世界の全体像を明確に提示する。それぞれの楽曲の素晴らしさ、メンバーの技術に支えられた演奏の確かさ、使用されたメロトロンやフルート、サックスといった楽器群の音の表情、グレッグ・レイクの歌唱の魅力、ピート・シンフィールドの歌詞の美しさ、そしてロバート・フリップによる時にアグレッシヴで時にリリカルなギター演奏の魅力、そうしたあらゆる要素のひとつひとつがこの作品の持つ魅力となり、それらが織り上げられ、組み上げられ、「クリムゾン・キングの宮殿」という類い希な傑作を形作っている。
「クリムゾン・キングの宮殿」は、その内包する音楽性の多様さ、表現された音像の表情の多様さ、意味深い歌詞の魅力などによって、思索的な深さを生み、聴き手に「鑑賞する」ことを許し、さまざまに「味わう」ことを許す。その音楽は衝動的でありつつ理知的であり、秩序と混沌とが同居し、野蛮と洗練とを兼ね備え、普遍的な「芸術」としての音楽作品へと高次に昇華されている。作品の「深み」は、鑑賞者のそれぞれに異なる心象を喚起させ、異なる解釈を生み、異なる意味を持たせる。この音楽がロック・ミュージックの土壌の中から生まれ、純然たるロック・ミュージックとして結実していることは、当時充分に「革新」であり、「挑戦」であっただろう。

「クリムゾン・キングの宮殿」はその全体を言いようのない閉塞感によって覆われているようにも感じられる。出口の無い闇の中で叫ぶような「21st Century Schizoid Man」の閉塞感、一条の光を求めて絶望の淵を歩くかのような「Epitaph」の閉塞感、何かの終焉を告げるかのような「The Court Of The Crimson King」、幻想的で美しい「Moonchild」も、牧歌的で安らかな「I Talk To The Wind」でさえ、その印象は解き放たれてゆくことなく暗く狭いどこかに閉じこめられたままだ。迷宮の中に囚われているかのような、聴き手の心に重く沈むこの閉塞感は何なのだろうか。この閉塞感こそがそれぞれの楽曲をひとつに織り上げて「クリムゾン・キングの宮殿」という一つの作品としている大きな要素であるかもしれない。
「クリムゾン・キングの宮殿」はその歌詞世界と音の表情が造り上げる印象のためか、幻想的な色彩に彩られ、まるで伝説に語られる世界に迷い込んだような感触もあるが、それと同時に日常の現実を異なる位相から見ているような異様なリアリティも感じさせる。幻想性のように見えるものも、実はすべて「現実」というものの持つ不条理さの別の表情でしかないのだと、その音楽は聴き手の心に鋭く迫る。この作品を覆う閉塞感は、ある意味では聴き手自身が「世界」というものに対して抱いている閉塞感そのものであるかもしれない。

「クリムゾン・キングの宮殿」は、時に「緻密に計算された構築美」といった形容をもって語られることがある。それぞれの楽曲の魅力、演奏の素晴らしさ、アルバムとしての構成の妙など、その圧倒的な完成度は、「構築美」という形容が相応しいものかもしれない。しかしこの作品は設計図に従って組み上げられる構築物のように制作されたものではあるまい。完成した姿が予め決められており、それを目指して造り上げられたものではない。
この作品は、乱暴な言い方をすれば、偶発的に造り出されてしまったものであるかもしれない。音楽的理想の元に集った五人の天才的才能が協調しつつ、時には競うように、試行錯誤の末に造り上げた所産としての形がこの作品であるだろう。楽曲の中に聴かれるインプロヴィゼイション的演奏は、それぞれの演奏者がまさに自由にイメージを膨らませた結果であるだろう。ある意味では、その演奏形態はジャズに近いものであったと言えるかもしれない。後にロバート・フリップはメンバーのインプロヴィゼイション・プレイが生む緊張を音楽の中心に据えてゆくが、その方法論はすでにこの時から彼の中にあったのに違いない。
五つの才能は核となるイメージをそれぞれに育み、互いに影響を与えつつ、同調し、何かに挑むように作品の創造へと向かったのだ。ひとつの「時代」を築き得たグループのほとんどがそうであるように、この時のキング・クリムゾンにもまた天才的才能の奇跡的な出会いが実現し、そのことがロック・ミュージック史上に燦然と輝くこの傑作の実現を可能にしたのだ。この作品を創造した才能たちは、この後二度とひとつの作品の創造の元に集うことはなかった。大仰な賛辞を惜しまないとすれば、「クリムゾン・キングの宮殿」という作品はロック・ミュージックに於けるひとつの奇跡である。
This text is written in January, 2002
by Kaoru Sawahara.
by Kaoru Sawahara.